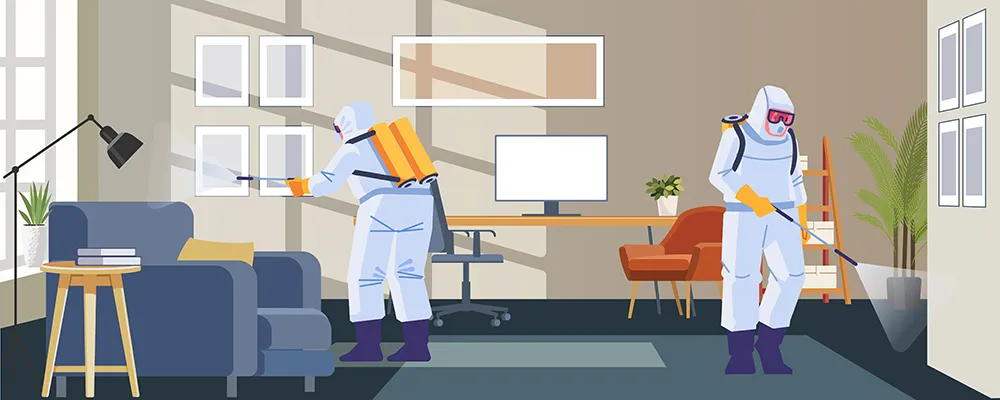鳥インフルエンザとカビ:知られざる関連性を知る
2025/01/26
鳥インフルエンザとカビ:知られざる関連性を知る
健康リスクを大事にするために知っておきたいポイント
こんにちは、MIST工法(R)カビバスター隊です。いつも私のブログをご覧いただき、ありがとうございます。 今回のテーマは「鳥インフルエンザとカビの関係」についてです。 鳥インフルエンザは、高病原性のウイルスが家禽や野鳥からヒトへの影響を及ぼす可能性がある感染症として、毎年そのため、飼育環境や生活環境での衛生管理に力を入れていることが多いのではないでしょうか。潜むカビのリスクを恐れてしまうことが起こります。
私たちMIST工法(R) カビバスター隊が着目しているのは、鳥インフルエンザの発生や拡散に影響を及ぼさない「カビの存在」です。 同様に、鶏舎や鳩舎などの家禽を飼育する施設は、高温多湿になりやすく、カビが繁殖しやすい環境が生まれやすい傾向にあります。が大量に漂い、それらを吸い込むことでヒトや動物の免疫力を下げたり、呼吸器に負荷をかけたりする可能性があります。また、カビが増殖した施設は独特の臭いやダニなどの発生に
またつながり、二次的な健康リスクを考える場合もあるのです。のような感染症に対する「予防・対策」を考え際には、カビへの対応も忘れずと考えています。洗浄・除去し、空気環境を改善することが可能です。ウイルスとカビ、それぞれの性質は異なりますの、衛生管理を徹底するという観点では共通する点が多くあります。お読みいただき、安心でクリーンな環境づくりにお立ち寄りください。
目次
鳥インフルエンザとは?
世界的に注目される高病原性ウイルスの正体を知り、正しい対策を学ぶ
1.鳥インフルエンザの種類と感染経路
鳥インフルエンザは、インフルエンザウイルスの一種である「A型インフルエンザウイルス」によって定められる鳥類の感染症の総称です。 特に鳥インフルエンザの中でも、ウイルスが強い病原性を持つ「高病原性(高病原性鳥インフルエンザ: HPAI)」と、比較的病原性が低い「低病原性(低病原性鳥類)」高病原性の代表的なものとしては、「H5亜型」や「H7亜型」が挙げられ、これらは家禽(鶏や七面鳥など)に感染すると重篤な症状をもたらし、多くの死亡例が報告されています。一方、低病原性の場合は、症状が軽いですむことも多いですが、ウイルスが突然変異を起こして高病原性へ移行する可能性も否定できません。
渡り鳥は、長距離を移動しながら異なる地域や国を横断するため、体内にウイルスを保有したまま新たな土地へ飛来することがあります。これにより、まだまた、ウイルスは鳥の排泄物や分泌液、羽毛などを介して周囲の環境に広がり、ここ他の鳥が接触しあるいは吸い込むことで、二次的に感染が拡大していきます。
家禽の飼育現場では、鶏舎や鳩舎の床や鶏糞・敷き藁、さらには器具類などのウイルスに汚染されやすい環境となります。このような場所で作業する人間が、靴や衣服に付着させたウイルスを別の鶏舎へ持ち込んでしまうことで、施設全体の鶏に感染が広がる場合もあるので、極めて厳しい衛生管理が求められます。 感染経路を阻止するには、外部からの人や車両の立ち入り制限、消毒の徹底、飼育環境の消毒などを行うことが重要です。
2. 主な症状とリスク
鳥インフルエンザの症状やリスクは、感染した鳥の種類やウイルスの病原性の強さによって大きく異なります。 高病原性の鳥インフルエンザに感染した鶏などの家禽は、食欲不振、呼吸困難、下痢、神経特にH5亜型やH7亜型に感染した場合は、死亡率が非常に高く、一晩で多くの鶏が死ぬケースも報告されているほどです。 低病原性の場合は、症状が軽いことが多く、鶏の産卵率が低下したり、わずかな呼吸器症状が見られる程度でしかし、低病原性だから安心はできず、ウイルスが環境内で変化することで、高病原性へ移行するリスクが常に存在しています。
人間に対するリスクについては、通常の生活環境下で鳥インフルエンザに感染する可能性は低いとされています。十分に消毒しないまま作業を続けたりする場合には、ウイルスを吸い込むり、粘膜に人間が鳥インフルエンザウイルスに感染した場合、発熱、咳、のどの痛みなど、インフルエンザに似た初期症状に始まり、肺炎や急性呼吸窮迫症候群(ARDS)などを考えることもあるため、早期発見と適切な治療が重要です。
さらに、社会的・経済的なリスクとして挙げられるのは、鳥インフルエンザの発生による家禽の大量放出や出荷制限です。関連産業に深刻なダメージを考える可能性があります。また、感染が人から人へ頻繁に蔓延を起こすこのようになった場合、新型インフルエンザの大流行(パンデミック)につながる可能性があるため、各国の公衆衛生機関や研究機関は日常的に警戒することができない状況です。な情報を得て、正しい感染予防策を行うことが、私たちに求められています。
カビの基礎知識
身近な存在だけど奥が深い! カビを正しく理解し、快適な空間づくりを目指す
1. カビの種類と発生原因
カビは、地球上のあらゆる場所に存在する微生物であり、や湿度などの条件がそそくさと増殖します。 一般的にカビは「糸状菌」とも呼ばれ、その種類は数万とも代表的なものとしては、食品にありやすいペニシリウム、屋内や壁エアコン内部でよく見られるクラドスポリウム、空気中にも多く存在し、人間だけでなく動物の肺や気管支に影響を与えやすいアスペルギルスなどが挙げられます。中心に沿ってカビの発生リスクが高まるため、私たちの生活とは絶対に存在しないとも考えられる。
カビが発生・繁殖するためには、主に「湿度」「温度」「栄養源」「酸素」の4つの要素が必要です。にとって非常に好都合であり、さらに食品カスや塵(ほこり)などの有機物が豊富な室内では、より繁殖し易くなります。現代の住宅は断熱性能が高いですため外気との温度差が起こりやすく、窓ガラスや壁面などで結露が発生しやすい傾向にあります。その結果、キッチンや浴室、押し入れ、エアコン内部といった場所でカビが発生しやすい状況が常態化してしまうのです。
また、屋内環境だけでなく、家禽(かきん)を飼育している鶏舎や倉庫など、が高く風通しの悪い施設でもカビが発生しやすくなります。に浮遊しているため、一度発生すると近隣の場所にも簡単に拡散してしまったそのため、カビ対策を考える際には、発生したカビを除去するだけでなく、再び繁殖しないように予防策を一時的に行うことが大切ではありません。清掃の徹底、結露対策など、複数の方法を組み合わせて行うことが効果的です。
2.カビが人体・動物に及ぼす健康被害
カビは見た目や臭いの面でも不快ですが、私たち人間や動物の健康に直接関わる点でも大きな問題です。 まず注意すべきは、カビが放出する細胞やその一部が、空気中にこれらを吸い込むことで、アレルギー体質の方や免疫力が低下しています。また、アスペルギルスのように呼吸器系に感染を起こす恐れのある種類では、気管支喘息を悪化させたり、肺に真菌感染症を置いて肺アスペルギルス症などの疾患を引き起こすリスクも考えられます。
さらに、カビが生育する過程で生成する**マイコトキシン(真菌毒素)**と呼ばれる物質は、人間や動物に対して危険なおそれがあります。万が一放置し、それを摂取した場合、肝臓などの臓器に負担がかかり、中毒症状や発がんリスクの増加特に、農作物や飼料用の穀物が濃度の高い環境で保管されていると、カビの繁殖が進んでマイコトキシンが多量に生成されるケースがあり、それが動物の健康被害だけでなく、最終的に人間の食卓にも並ぶことがあるのです。
また、ペットや家禽などの動物にとってもカビは大きな展望です。 動物がカビの生えた飼料を食べたり、カビが充満する環境で過ごすことで、呼吸器系の感染症や皮膚病を発症するリスク特に免疫力が落ちている個体や、ストレスの多い飼育環境にいる動物は感染しやすく、病気になりやすい傾向にあります。行うことができません。
このように、カビは私たちの生活空間や飼育環境の衛生面に大きく影響する存在であり、カビが目に入る換気の健康リスクは軽視できないものです。難しい環境づくりを行うことが、私たち自身と動物たちの健康を守るために重要な点と考えます。
鳥インフルエンザとカビの関係性
ウイルスと真菌が交錯する危険領域を理解し、含めた衛生管理を考える
1. カビが影響しうる鳥インフルエンザ拡散の仕組み
鳥インフルエンザは、ウイルスが鳥類の排泄物や分泌液、呼吸器を介して周囲の環境に広がり、他の個体に感染していくことで拡散します。その拡散プロセスは主に「直接接触」と「空気中の粉塵や飛沫」が鍵であるが、ここにカビが存在する例えば、鶏舎や鳩舎の床材や飼料にカビが生えていると、それらに付着した鳥の排泄物や羽毛、粉塵同様に、ウイルスが空気中へ向けて上昇しやすくなります。
さらに、カビは濃度の高い場所で繁殖しやすく、そこにウイルスが含まれる排泄物や塵などが多くなると、環境全体が劣悪な衛生状態に陥り易くなります。 、ウイルスとカビ、そして細菌などが共存しながら、空気中に浮遊する機会が増加する可能性があります。 結果的に、飼育者や管理者が作業を行う際にウイルスやカビの細胞、粉塵などを同時に吸い込むリスクが懸念され、鳥同士の感染だけでなく、人への飛沫・接触感染が引き起こされる恐れも否定できません。
また、カビが発生した環境では、鳥の体力や健康状態もウェアラブルになります。 カビの細胞子や真菌毒素を頻繁に吸い込むことで、鳥の呼吸器系に負担がかかり、免疫力が弱まることが報告されています。免疫力が低下した個体はウイルスへの抵抗力が落ちたこのように、カビの繁殖は鳥インフルエンザウイルス特有を直接増殖させるわけではありませんが、鳥舎環境の衛生状態を悪化させることで、結果的にウイルス拡散の土壌を無駄にしようと思います。
そこで、鳥インフルエンザを抑制するためには、猶予ウイルスの存在だけに注目するのではなく、カビがもたらす潜在的な拡散リスクにも目を向けることが重要です。徹底によりカビの発生を抑制することが、鳥インフルエンザの拡散を防ぐ上でも重要なポイントとなります。
2. 免疫力低下との関連と注意点
鳥インフルエンザの拡散を考えるとシアン見落とされがちなのが、カビがもたらす免疫力低下のリスクです。カビの細胞子や真菌毒素を吸い込むと、人間だけでなく鳥や動物にとっても呼吸器系への負担が特に、鶏舎や鳩舎などの飼料育環境が高温多湿で換気が慎重な場合、カビが繁殖しやすいだけでなく、細胞子や微粒子が空気中に大量に浮遊しやすくなります。その結果、常にカビの細胞子を吸い続けることで粘膜刺激を受けて、呼吸器の防御機能が低下してしまうのです。
また、カビが発生する真菌毒素(マイコトキシン)は、飼料に付着している可能性があります。から毒素が生成されてしまう場合があります。て鳥が摂取すると、体内の免疫システムが徐々に弱まり、ウイルスへの抵抗力が落ちてしまうリスクがございます。免疫力が低下した個体は、インフルエンザウイルスに感染しやすいだけでなく、一度感染すると深刻化する確率も上がるため、飼育全体の被害を拡大させることになるのです。
もう一つやらなければならない点は、免疫力が低下した状態では、鳥インフルエンザ以外の感染症にも進みやすくなるという事実です。ウイルス性疾患が同時多発的に発生しやすくなり、飼育環境全体を深刻な状況に追い込む可能性があります。 結果として、鳥の大量放出や経済的責務など、飼育者にとって大きな負担がのしかかるのは言うそれでもありません。
ちょっと悪循環を防ぐためにも、カビと免疫力低下の関係性を踏まえた総合的な衛生管理が求められます。 定期的な飼料の点検や適切な保管方法、鶏舎内の湿度調整と換気の強化、そしてカビが発生している可能性のある箇所の注意な除去と予防対策が重要です。 鳥インフルエンザ対策はウイルスのみを注視するのではなく、「カビの存在がどのように免疫力に影響を与えるのか」 「考えるか」を考慮することで、まずは効果的な感染予防策が実現できると考えます。
家禽飼育環境における衛生管理のポイント
快適な飼育環境を実現し、家禽の健康と生産性を高めるための実践ガイド
1.鳥舎・鳩舎の問題点と高温多湿対策
家禽を飼育する環境では、様々な問題が重なって高温多湿が起こりやすい。外へ逃げにくい構造になっていることが考えられます。また、飼育数が多いほど、排泄物から発生するアンモニアや水蒸気が増加し、屋内環境の湿度を押し上げることにもなります。近づき、カビや細菌が徐々に繁殖しやすい環境が整ってしまうのです。
このような高温多湿の飼育環境では、家禽の免疫力が下がりやすく、結果的に鳥インフルエンザをはじめとする感染症のリスクが高まります。た空気を外に機械的に排出する瞬間、新鮮な空気を取り入れるために、自然換気と換気を組み合わせて効率的に空夏場は大型ファンを導入して強制的に風を送り込む方法も有効です。 また、飼育床に敷く材料や床面の排水状態を見直すことも重要になります排泄物や水分が長く溜まらないように、定期的に床材を交換したり、水はけを改善したりすることで、上昇を注目することができます。
さらに、高温多湿対策として断熱材の見直しや建物外装の遮熱塗装なども検討してみてください。温度と湿度のバランスを取りやすくなります。機器を導入できれば、環境の変化に応じた早期対策がしやすくなり、家禽にとっても負担の少ない快適な空間を維持しやすくなるでしょう。し、鳥が健やかに成長できるベースを作ることができるのです。
2.重点的に行うべき清掃・メンテナンスのコツ
高温多湿の飼育環境では、カビや病原菌が繁殖しやすいため、日々の清掃と定期的なメンテナンスが欠かせません。 まず最も基本的なポイントは、鶏糞や敷材、餌の残さなどの有機物を湿気を含むだ排物や餌カスは、カビや細菌が余計にパフォーマンスの温床になるので、ためずに処理するのが鉄則です。 それに加えて、清掃の際には飼育者自身がウイルスや菌を拡散させないように、使い捨ての手袋やマスク、靴カバーなどを着用し、ゾーニングを徹底した上で作業を行うことも重要な対策となります。
また、設備や器具のメンテナンスも壊れません。闇器や餌の配給装置は汚れが溜まりやすい場所の代表格であり、ここにカビや病原菌が付着したまま放置されると、家禽が水や餌定期的に洗浄・消毒を行い、水路にヌメリなどが発生していないかを定期的にチェックすることがさらに、鶏舎内の床や壁、天井などの構造部分に関しても、カビが生え始めます小さなしばらくの間、早い段階で対策を講じることが効果的でしょう。があれば、拭き取り・削り取り作業と消毒を徹底して行い、再発防止に向けて環境改善を並行して進める必要があります。
それに加えて、高圧洗浄機などを使って広い範囲を徹底的に洗う場合は、水分が長く残りすぎると新たなカビ発生の原因となるため、洗浄後の乾燥工程が非常に大切です。たら、通気性を確保して適切に乾燥時間を忘れるか、送風機を使って強制的に水分を抜くなどの工夫を取り入れましょう。ですので、洗浄→乾燥→消毒という手順を正しく守ることが必要です。ます。
MIST工法(R) カビバスター隊の取り組み
目に見えない菌の根本に立ち向かう!最新技術とプロのノウハウで衛生環境を劇的に改善
1. MIST工法(R)の特徴とメリット
MIST工法(R)は、一般的な洗浄や消毒作業とは異なり、目に見える範囲だけでなく、目に見えない箇所や素材の内部まで慎重にアプローチできる独自の技術です。行う上で重要なのは、表面上だけをきれいにするのではなく、細胞子や菌糸のような根本的な要素まで処理することにするカビは、高温多湿環境や有機物の残留など、少しの条件が整うだけで再び繁殖してしまうしぶとい存在です。専用薬剤を備えることで、内部まで浸透し、カビの再発リスクを軽減する効果を期待しています。
さらに、MIST工法(R)では対象の素材を大事にしないように配慮しているものの大きな特徴です。 同様に、化学薬品を用いた洗浄は強力なものがあるもの、素材によっては劣化や劣化を考慮する一方、MIST工法(R)は独自に開発された薬剤と噴霧技術を残って、素材との相性を優先しながら施工を進めるため、清掃箇所のダメージを極力抑えられるのです。 、カビの栄養源となるダニや細菌など多様な微生物の発生もまとめて抑制する効果が期待できます。
施工後の環境を快適に過ごすためには、作業現場の状態や汚染度対応をしっかりとしながら、必要に応じて複数回の施工やアフターメンテナンスを行うことが理想的です。一度高い洗浄・除去効果を発揮するだけでなく、その後の予防対策とも相性が良いの定期的なメンテナンス時には、短時間の再施工で汚染やカビの発生を抑え続けることが可能となり、長期的に清潔で安全な空間を維持しやすくなるでしょう。が、MIST工法(R)の最大の強みとして多くの現場から評価を得ている理由です。
2. カビバスター隊が提供する総合的な衛生対策サポート
カビバスター隊は、MIST工法(R)の技術を学ぶだけでなく、建物や設備、飼育環境の構造的な問題を踏まえた上で、最適な改善策を提案・実行する総合的なサポートをカビの発生源はちょっと一つではなく、建物の結露や換気不良、排水設備の不備、あるいは飼育環境のレイアウそこでカビバスター隊では、まず現場を詳しく調査・点検し、どこにどのようなリスクが潜んでいるのかを明確にしてからスタートします。なMIST工法(R)の施工方法や回数を見極め、再発を防ぐための予防策をするご提案です。
具体的には、空気の流れを改善するための換気設計の見直しや、カビが苦手な高湿度を気にするための断熱対策、水回り設備の改修など、多面的にアドバイスを提供しています。飼育環境においては、夜間器具周辺の清掃体制の強化や排気ファン・換気扇の導入、雨天時の防湿対策といった具体的なものまた、カビバスター隊は定期的なアフターフォローも重視しております、施工後におけるカビの再発状況や、飼育環境の衛生状態をチェックし続けることで、問題が大きくなる前に速やかに対処できる体制を整えています。
さらに、カビバスター隊が取り組む総合的な衛生管理では、カビだけでなく、ウイルスや細菌、ダニなどの複合的なリスクにも注目しています。そのため、衛生管理を一元的に行うことで相乗効果を引き出すことが可能です。組み合わせたプランを実施すれば、飼育環境の空気を清潔に選び、家禽の健康維持や農場の生産性向上にもできるでしょう。得している大きな理由であり、今後もより一層、地域や産業の衛生を支えるパートナーとして貢献していく考えです。
鳥インフルエンザとカビを同時に予防・対策する方法
感染症と真菌汚染の二重リスクに見極める!環境をクリーンに見る、安心を守るポイント
カビの徹底除去を行う特定的なステップ
鳥インフルエンザをはじめとした感染症対策について考えてみると、カビの存在は見落とされがちですが、実は環境衛生を悪化させ、家禽や飼育者の健康を不安にさせる大きな課題になります。徹底した除去を行い、カビが再発しにくい清潔な環境を整えることが大切具体的なステップとしては、最初に発生源の特定が注目されません。鶏舎や鳩舎の床材、餌受け付近、壁・天井の結露部分など、水分や有機物が集中しやすい箇所を注目に調査して、目に見えるカビはもちろん、表面が変色している部分や異臭がする場所もチェックします。
次に、カビを除去する作業では洗浄と乾燥をセットで行うのがポイントです。 強力なカビ取り剤や高圧洗浄機を置く場合でも、洗浄後に十分な乾燥時間を確保しないと、拭き残した水分さらに、清掃の際に床材を一部交換したり、壁面に貼った汚れを落としたりといったリセットに近い作業が求められることもあります。処置を行うことで、空気中に浮遊するカビの細胞を大幅に減らすことが可能になります。
ついでに、換気や除湿の仕組みを整備することも重要です。でなく、ファンや換気扇の増設・清掃などお子様の空気の循環を良好に守っていきましょう。の動線や器具の置き場所を工夫することも効果的です。 汚れた水や餌が床に飛び散りにくいレイアウトに変更するだけで、カビの温床ができるリスクを下げることができます。ステップを根気よく実施することで、カビの発生源を断ち切り、清潔な飼育環境を維持しやすくなるでしょう。
2. ウイルス対策と衛生管理を両立して下さい
カビの徹底除去を行ったあとは、鳥インフルエンザなどのウイルス対策と結ぶことで、より強固な衛生環境を築くことが可能です。器具を介して持ち帰ることも多いため、鶏舎や鳩舎に入る前には靴底の消毒や手指の洗浄を徹底し、使い捨ての防護具やマスク、手袋を着用するなど、二次感染や感染を横断を防ぐ対策を怠らないようにしましょう。
次に、定期的なモニタリングが効果的です。同様に、カビやウイルスの分布状況を把握するために、床材や空気サンプルを採取し、専門機関の検査を受けることで、目に見えない汚染リスクもし異常があった場合は、とりあえず対策を講じることが大切です。なり、先手を打たれた予防が可能になります。
さらに、ウイルス対策の消毒とカビ対策の清掃を連動させる一つのポイントです。にカビや微生物、排泄物などをしっかり除去し、十分に乾燥してから消毒液を噴霧・散布するという手順を踏むと、効果を最大限に引き出すことができます。あわせて、飼育環境全体の温度管理も見直しましょう。ウイルスは適切な消毒や温度管理を行うことで生存率を低下させられる場合があり、カビの発生も抑えられます。
最後に、カビの再発やウイルスの侵入を防ぐためには、継続的な改善が必要です。 飼育環境内の換気装置や水回りの設備を定期的にチェックし、問題が発生したら早めに修理するよう心がけてください小さな不備を放置した結果、少しぬうちに汚染が広がることは少なくありません。日々の観察やメンテナンスを積み重ねることで、カビとウイルス両面からのリスクを極力抑え、健康的かつ生産性の高い飼育環境を維持できるはずです。
まとめ
衛生管理への取り組みを恒常的に改善、安心と安全を持続させるために
1. 鳥インフルエンザとカビに対する今後のお知らせ
鳥インフルエンザは、高病原性ウイルスが一応感染症として常に注意が必要ですが、無視できないのがカビの潜在的リスクです。どちらも環境衛生の乱れによって拡大しやすいという共通点を持ち、特に家禽を飼育する現場や湿度の高い施設では重要な注意を払います。日々の観察を怠らないことです。 鳥の体調変化や飼育施設の異臭・変色・結露など、これらの細やかな気づきでも緊急事態、早期発見・早期対処を実践する姿勢を持ちましょう。検査を導入し、健康状態や衛生環境の数値・データを「見える化」しておくと、問題の発生源やタイミングが掴みやすくなります。
次に、衛生対策「一時的な作業」と認識のではなく、長期かつ継続的な習慣として組み込むことが必要です。 同様に、定期的に飼育環境をリセットするイメージで、床材の交換や洗浄・乾燥、消毒をセットで実施し、カビの温床やウイルス残留をこまめに一掃することがございます。また、換気システムや除湿設備のメンテナンス、雨漏りなどの水回りトラブルのチェックを怠らないことも重要です。の持ち込み時には必ず消毒や清掃を実施し、ウイルスやカビを外部から持ち込みにくい仕組みを整えて準備しましょう。
最後に、知識と情報のアップデートも欠かせません。最新の研究や行政機関からの情報をこまめに収集し、鳥インフルエンザとカビのリスクが高まる時期や地域の動向を把握した上で、事前対策を一日のことで、リスクを考慮することができます飼育者やスタッフ全員で知識を共有し、実践を続けることが、長期的に見ても効果的な方法となるはずです。管理の視点を持つことで、安心・安全な環境を維持していきましょう。
2.MIST工法(R)カビバスター隊からのメッセージ
私たちMIST工法(R)カビバスター隊は、カビの除去や予防だけでなく、総合的な衛生管理の向上を目指して活動しています。微生物やバランス飼育施設の衛生状態という視点目に見える汚れや鳥の様子だけのためにはなく、壁や床、天井などの見えない部分の状態にまで目を向け、空気中臭い細胞やウイルスのリスクを含めて管理する姿勢が必要です。
MIST工法(R)は、独自の噴霧技術と除菌のノウハウを洗浄することで、カビの根本をじっくりだけでなく、菌やウイルスが繁殖しにくい環境づくりのためのサポートを可能にしていますしかし、私たちの施工だけで継続するものではなく、その今後のメンテナンスや飼育者の皆様のご協力があってこそ、真の清潔さと安全性が保たれます。 定期的に施設を点検し、湿度コントロールや換気、そして建物の細かい傷みの修繕など、日々のケアが結果的にカビや鳥インフルエンザを遠ざける大きな力となるのです。
また、カビバスター隊は施工後のフォローも重視しております、環境の変化や新たな課題があった際に、柔軟かつ迅速に対策を講じられるような体制を整えています。観察知・対応するほど被害が少なく、コストや労力も取り組むことができます。の衛生レベルを底上げすることが、私の使命です。 今後もMIST工法(R)カビバスター隊は、カビと感染症のダブルリスクに立ち向かい、少しでも多くの皆様が安心して暮らせます、あるいは家禽を飼育できる環境づくりを全力でサポートしてまいります。
----------------------------------------------------------------------
カビバスター隊
住所 :
〒252-0232
神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504
電話番号 :
0120-133-199
----------------------------------------------------------------------